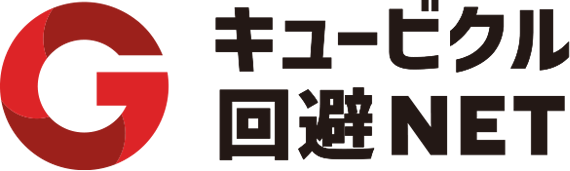キュービクルって環境に悪影響?電気設備とエコの関係
キュービクル=高圧受電設備というと、「大きな機械だから、もしかして環境に悪いのでは?」というイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし、実際にはどうなのでしょうか?今回はキュービクルが環境に与える影響について、わかりやすく解説します。
そもそも「キュービクル」が環境に与える影響って?
まず、前提としてキュービクルそのものは「電気を高圧から低圧に変圧する装置」です。
電気を発生させる装置ではないため、単体で二酸化炭素(CO₂)などの温室効果ガスを排出することはありません。
しかしながら、環境面での影響を考えるうえでポイントになるのは以下の3つです。
| 項目 | 環境への関係性 |
|---|---|
| 製造・設置時の資源消費 | 鉄・銅などの金属資源、工事でのCO₂排出 |
| 運用時の電力効率 | 変圧・配電のロス(電力のロス) |
| 廃棄時の処理 | 産業廃棄物としての適正処理が必要 |
つまり、「直接的な環境負荷は小さいが、製造~運用~廃棄のライフサイクルで見れば影響ゼロとは言えない」というのが正確な理解になります。
エネルギーロスという視点で考える
キュービクルは、6600Vの高圧電力を各店舗が使えるように100V~200Vに変圧する役割を持っています。
この変圧の際にはわずかながら熱としてエネルギーが逃げる(ロス)が発生します。
とはいえ、変圧ロスは全体の数%以下であり、大規模施設ではむしろ高圧受電の方が総合的にエコになる場合が多いです。
たとえば複数店舗でキュービクルを共用している商業施設では、まとめて電気を受けることで、個別契約よりも電力効率が良くなるケースもあります。
使用電力との“間接的”な関係
もう一つの視点は、キュービクルが使う電気自体の“出どころ”です。
キュービクル自体が電気を作るわけではなく、電力会社からの供給を分けているだけですが、その供給元が火力発電であれば、間接的にはCO₂を排出している電気を使っているということになります。
そのため、近年では
- 再生可能エネルギーによる供給に対応できるか
- 太陽光などの自家発電との連携は可能か
といった「エネルギー源の選択肢を広げるための装置としてのキュービクル」が注目されるようになってきました。
廃棄・更新の際は“適正処理”がカギ
キュービクルの耐用年数はおよそ20~25年とされており、それを超えると更新(入れ替え)が必要になります。
このときに重要なのが、使用済みのキュービクルの処理です。
- 鉄・銅・絶縁油などが含まれるため、産業廃棄物として専門業者が適正に分解・回収する必要があります。
- 特に古い機種には、PCB(ポリ塩化ビフェニル)という有害物質が使われている可能性もあり、事前確認が大切です。
つまり、適切な廃棄プロセスを踏まないと、環境負荷が一時的に高くなる可能性があるという点には注意が必要です。
逆に“環境に良い”面もある?
一方で、キュービクルの存在が環境配慮に貢献している側面もあります。
再エネやEV充電器との連携が可能
- 自社で太陽光パネルを設置したい場合でも、専用のキュービクルで連系が可能になります。
- EV充電設備など高電力を必要とする装置の導入にも、キュービクルがあることで対応しやすくなります。
ピークカット機能との組み合わせで省エネも
- デマンド監視(最大使用電力)と連動させることで、電力使用の平準化(ピークカット)に貢献できます。
- これは電力供給全体の安定化=発電所の負担軽減=環境負荷の低減にもつながります。
まとめ
キュービクルそのものが環境に大きな悪影響を与えるわけではありませんが、製造・運用・廃棄のそれぞれで環境への影響がゼロではないのも事実です。
しかし、近年ではキュービクルを活かして再生可能エネルギーの受電やEVインフラと連携するケースも増えており、むしろ環境配慮のインフラの一部として期待される場面もあります。
つまり、「キュービクル=環境に悪い」というよりも、「使い方次第で環境に優しくもなる装置」と捉えることが大切です。
キュービクルの設置に迷ったらまずは当社にお問い合わせください!