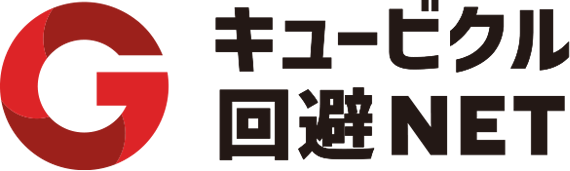キュービクルの更新タイミングってどう決める?
「キュービクルの調子が悪くなってから交換すればいい」そんなふうに思っていませんか?
しかし実際には、「壊れてからでは遅い」のがキュービクルです。
火災や停電といった重大トラブルを避けるためにも、計画的な更新が重要です。
では、どのタイミングで交換すればよいのでしょうか?その目安や判断基準を解説します。
一般的な耐用年数と「法的な基準」
まず基本となるのが、キュービクルにおける法定耐用年数と呼ばれる数字です。
- 法定耐用年数:15年(法人税法)
- メーカー推奨/物理的寿命:15年~20年程度
※ただし、使用環境やメンテナンス状況によって異なり、適切な保守を行うことにより法定耐用年数を超えて使用することは可能です。
現場では20年超使い続けているケースも珍しくない一方、早期に更新すべきと判断されるケースもあります。
更新タイミングの目安になるサイン
以下のような状況が見られたら、更新や大規模な修繕を検討すべきタイミングです。
年数ベースでの目安
| 使用年数 | 状態と対応の目安 |
|---|---|
| ~10年 | 点検中心でOK、部品の劣化に注意 |
| 10~15年 | センサー系や継電器など、消耗部品に故障が出始める |
| 15~20年 | 主機器の老朽化リスク上昇、更新計画の検討開始 |
| 20年超 | 想定外トラブルのリスク高、更新推奨フェーズ |
※あくまで目安ですので使用環境やメンテナンス状況によって変わります
状態ベースのサイン
- 開閉器の動作音が変わった・鈍くなった
- 絶縁油の劣化(色・匂い)
- 鉄部のサビ・腐食が目立つ
- 異常な発熱(触れないほど熱い)
- 漏電・トリップの頻度が増えた
これらが見られたら、点検だけで済ませず「更新の見積もり」を取ることを検討した方が良いでしょう。
更新にはどれくらいの費用・期間がかかる?
キュービクルの更新工事は、数十万円~数百万円単位の工事になります。
ただし、契約電力や容量、設置場所(屋内外)によって大きく異なります。
費用目安(一般店舗規模)
| 低圧受電からの切替導入 | 200万~300万円 |
| 高圧受電キュービクル更新 | 150万~400万円 |
| 諸費用(設計・申請・電力会社協議など) | 別途 |
また、電力停止を伴うため、店舗休業との兼ね合いも大きな判断材料です。
ゴールデンウィークや年末年始の工事は避けたいなど、時期調整も含めて半年以上前から計画するのが理想的です。
更新するメリットと、しないリスク
更新には当然費用がかかりますが、それ以上に「更新しないことのリスク」が深刻です。
<更新するメリット>
- 火災・感電などの事故防止
- 最新の省エネ・保守性向上モデルへ移行可能
- 保険対応・補助金対応しやすくなる
- 管理コストやトラブル対応の手間が減る
<放置するリスク>
- 突発停電→営業停止
- 火災・漏電による人身事故
- 感電事故で労災認定の可能性
- 保守業者が修理対応できない場合がある(部品製造終了)
具体的な「更新判断の流れ」
更新するかどうかの判断は、以下のステップで進めていくのが一般的です。
- 点検業者へ診断依頼(年次点検・精密点検)
- 診断結果をもとに劣化度の報告書を取得
- 更新 or 修繕の費用を比較検討
- 工事時期・電力停止の調整
- 更新工事実施(申請→設計→工事)
このとき、複数業者の意見を聞くことが非常に重要です。
一社だけだと「本当に交換すべきなのか」が見えづらいため、セカンドオピニオンを取るのが鉄則です。
キュービクル更新の補助金ってある?
自治体や国の補助金制度が適用できるケースもあります。
例えば
- 中小企業向け省エネ補助金
- デジタル・DX設備更新支援補助金
- 防災・減災対策としての設備更新補助金
たとえば「老朽化による電力トラブルをIoT化で防止」という目的であれば、AI・IoT対応の新型キュービクルを導入する際に補助対象になる可能性があります。
更新時には、補助金に詳しい業者を通して相談してみるのがよいでしょう。
まとめ
- 更新の目安は15~20年が一般的
- 劣化のサイン(異音・発熱・錆など)があれば早急に診断を
- 更新には費用と準備期間が必要だが、事故や休業のリスク回避につながる
- 補助金制度を活用することで、コストを抑えた更新も可能
- 点検+複数業者の意見をもとに、計画的な判断を!
キュービクルの設置に迷ったらまずは当社にお問い合わせください!
【この記事の監修】
株式会社エネシフト(キュービクル回避ネット運営会社)
丸山 賢司 電気容量コンサルタント/国家資格:第二種電気工事士
約20年建築関連・電気関連の職務に従事。
製パン・製菓業界を中心にキュービクル回避を始め電気容量コンサルタントして数多くの店舗、会社を支援。
現在は業界外の電気容量対策支援とキュービクル回避の普及を行っている。
「自分の仕事で誰かを幸せにする」をモットーに日々の職務に励んでいる。