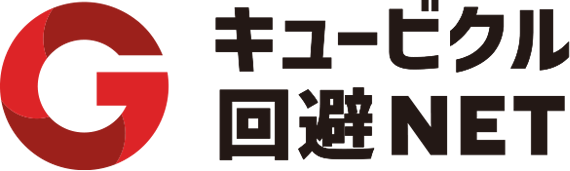キュービクルの寿命ってどれくらい?
ビルや店舗、工場などで使われるキュービクル(高圧受電設備)は、24時間365日、施設の電力を陰で支える「小さな変電所」です。
普段は意識されることの少ないキュービクルですが、老朽化によるトラブルや事故が起きる前に、きちんとその“寿命”と向き合っておくことが、結果的にコスト削減や安全確保につながります。今回は、キュービクルの寿命とその見極め方、そして寿命を延ばすための方法について解説します。
キュービクルの寿命は「20年」が目安
一般的に、キュービクル本体の寿命はおよそ20〜30年といわれています。ただし、これはあくまで使用環境やメンテナンスの状態に大きく左右される目安。屋内に設置されていたり、定期点検がきちんとされていれば30年以上稼働している例もあります。一方で、屋外で雨風や塩害の影響を受けている場合、15年程度で更新が必要になるケースもあります。
部品ごとに違う“寿命”のサイン
キュービクルは箱型の設備に見えますが、中には様々な部品(トランス、遮断器、避雷器、コンデンサなど)が収まっています。これらの部品にもそれぞれ耐用年数があり、一部が寿命を迎えることで全体の機能が低下するリスクも。
たとえば、トランスは20〜30年が目安。遮断器や避雷器は15〜20年、コンデンサは10〜15年ほどで劣化が進むとされています。これらの部品の劣化サイン(発熱、異音、サビ、電圧の不安定化など)を見逃さずに、計画的な交換をすることが寿命を延ばすカギです。
設置環境で差が出るキュービクルの寿命
キュービクルの寿命に大きく関わるのが「設置場所」です。屋内設置に比べて屋外設置では、雨、風、紫外線、気温差などにさらされ、機器内部に結露やサビが発生しやすくなります。特に海岸沿いや工場地帯では塩害やガスによる腐食の進行が速く、通常よりも早期のメンテナンス・更新が求められます。
寿命が近づくと何が起きる?
キュービクルが寿命を迎えると、漏電、感電、設備火災、広範囲停電などのリスクが高まります。最悪の場合は人身事故や、電力会社側にまで波及する停電トラブルを引き起こすことも。これにより、修理費だけでなく、営業停止や賠償金という大きなコストが発生するケースもあります。
いつ交換すればいい? 見極めのポイント
設置後15年を過ぎたあたりから、「更新」を視野に入れるべきと言われています。20年を超えると故障リスクが一気に高まり、かつメーカーの部品供給も終了しているケースが多くなります。定期点検の結果や、機器の不調が頻発しているなどの兆候が見えた時点で、計画的な更新を進めることが重要です。
寿命を延ばすには? メンテナンスの力
寿命を延ばす最大の対策は「定期的な保守点検」です。月次・年次の点検を怠らず、異常が見つかれば早期対応。屋外の場合は防水・防錆対策を行い、湿気がこもる環境ではヒーターや除湿機の設置も有効です。
また、部品単位での先回りした交換や、専門業者との保守契約を結ぶこともおすすめ。特に「うちは知識も人手もない」という事業者にとって、信頼できる保守パートナーの存在はキュービクルの“延命”において非常に大きな価値を持ちます。
まとめ
「壊れてから考える」では遅いのがキュービクルの怖いところです。
見た目に異常がなくても、20年が近づいたら“そろそろ交換”を考え始める。
これが、安全で安定した電力供給を維持するための最良の選択です。キュービクルの寿命と向き合うことは、未来のトラブルを防ぐ最初の一歩です。